長崎県をホームタウンとするV・ファーレン長崎は、Jリーグの中でも地域密着を掲げ、サッカーを通じて長崎県の活性化に取り組んできたクラブです。
しかし、これまで使用してきたスタジアムの規模や施設面での課題があり、クラブの成長と地域の発展を見据えた「新スタジアム構想」が長年議論されてきました。
2024年、新たなスタジアム「PEACE STADIUM Connected by SoftBank」が完成し、クラブだけでなく地域全体にとって重要な転換点となりました。
本記事では、新スタジアムが誕生するまでの経緯や、その魅力的な工夫について詳しくご紹介します。
新スタジアム建設までの経緯
V・ファーレン長崎が新スタジアム構想を本格的に打ち出したのは、2010年代後半のことです。
当時使用していた「トランスコスモススタジアム長崎」は、収容人数やアクセスの面で限界があり、クラブの目指す「J1定着」や「地域活性化」の目標を支えるには十分ではありませんでした。
また、長崎県全体が人口減少や経済停滞といった課題に直面する中で、スタジアムを中心とした新たな地域振興のモデルが求められていました。
そんな中、クラブオーナーであるジャパネットホールディングスの積極的なリーダーシップのもと、新スタジアムプロジェクトが具体化しました。
このプロジェクトの核となったのが、「スポーツを通じて地域の未来を創る」というビジョンです。
スタジアムは単なる試合会場ではなく、地域住民や観光客が集い、賑わいを生む「まちづくり」の拠点として位置づけられました。
建設にあたっては地元自治体や企業、そしてサポーターを巻き込んだ形で進められ、多くの困難を乗り越えて2024年に開業を迎えました。
このスタジアムプロジェクトは、スポーツビジネスと地域経済の融合を実現する先進的な事例として注目されています。
長崎スタジアムシティの革新と特徴

新たに誕生した「長崎スタジアムシティ」は、V・ファーレン長崎のホームスタジアムであると同時に、多機能型複合施設として地域全体に貢献することを目的としています。
その特徴的なポイントを以下に挙げます。
1. 地域住民と観光客のためのアクセス性
スタジアムは長崎駅から徒歩圏内に立地しており、公共交通機関を利用したアクセスが大幅に改善されました。
これにより、地元住民だけでなく観光客も気軽に訪れることが可能となり、試合観戦だけでなく地域全体の回遊性が向上しました。
また、試合日に限らず、日常的な利用を促進するための工夫が施されています。
2. サッカー専用スタジアムでの臨場感ある体験
長崎スタジアムシティは、観客とピッチの距離を最小限に抑えた設計を採用。
これにより、サポーターは選手たちのプレーを間近で感じられる臨場感あふれる観戦体験が可能となりました。
さらに、全席に屋根を設けることで、天候に左右されることなく快適に試合を楽しめます。
視覚や音響の工夫も施され、試合の迫力を存分に味わえる空間が実現しました。
3. 地域に根差した複合施設
スタジアム内外には、飲食店やショッピングエリア、宿泊施設が併設されています。
特に地元長崎の食材を活かしたレストランや土産物店が多数入居しており、試合観戦以外でも訪れる価値のある施設となっています。
また、会議室やイベントスペースも備え、ビジネス利用や地域行事の開催にも対応可能。これにより、スタジアムは地域コミュニティの中心的な存在となっています。
地域とクラブの未来
長崎スタジアムシティの完成は、V・ファーレン長崎だけでなく、地域全体の未来にとって大きな意味を持ちます。
試合日はもちろんのこと、日常的な利用を見据えたスタジアム運営により、地元経済の活性化や雇用創出が期待されています。
また、アクセス性の向上に伴い、県外や海外からの観光客を呼び込むことで、長崎県全体の魅力を高めるきっかけとなっています。
さらに、スタジアムの成功は、サッカーを通じた地域づくりのモデルケースとして全国の他地域にも影響を与えるでしょう。
長崎スタジアムシティは、スポーツと地域振興の可能性を象徴する存在として、新たな挑戦を続けていくことが求められます。
まとめ

V・ファーレン長崎の新スタジアム構想は、単なるスポーツ施設の建設にとどまらず、地域全体の活性化を目指した壮大なプロジェクトでした。
長年の議論を経て完成した「長崎スタジアムシティ」は、クラブと地域社会が一体となり築き上げた未来への礎です。
このスタジアムを拠点として、V・ファーレン長崎がさらなる飛躍を遂げると同時に、長崎県全体が新たな魅力を発信し続けることを期待しています。



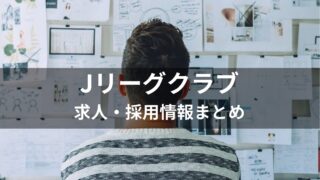



コメント